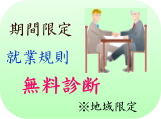
林社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士
産業カウンセラー
キャリア・コンサルタント
林 邦彦
迅速・丁寧をモットーに、お客様の労務管理に関する相談相手として、豊富な実績があります。
〒241-0004
横浜市旭区中白根3-20-7
TEL 045-955-3970
E-mail
info@sr-office-hayashi.com
|
|
|
会社などで働く人たちが収入に応じて保険料を出し合い、いざというときの生活の安定を図る目的で作られた制度のことで、一般的に健康保険や厚生年金のことを「社会保険」といいます。
健康保険法第1条では「労働者の業務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産及びその被扶養者の疾病、負傷、死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。」と定めています。
また、厚生年金保険法第1条では「労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とし・・・ 必要な事項を定めるものとする。」と定めています。
健康保険と厚生年金保険は、労働者個人や事業主が自由に契約・加入するものではなく、法律により加入が義務付けられています。
そのため、健康保険と厚生年金保険への加入は、事業所単位で行うことになり、事業主は従業員と保険料を折半して負担し、その納付や加入手続きなどの義務を負います。
健康保険と厚生年金保険は、事業所を単位として適用することになりますので、常時5人以上の従業員が働いている会社、工場、商店、事務所などの事業所と5人未満であってもすべての法人事業所は、法律によって事業主や従業員の意志に関係なく加入しなければなりません。
なお、5人未満の個人事業所と5人以上であってもサービス業の一部や農業、漁業などの個人事業所は強制加入の扱いとはなりません。
従業員が5人未満の個人事業所等でも、一定の要件を満たせば地方社会保険事務局長の認可を受けて健康保険と厚生年金保険の適用事業所となることができます。
任意適用事業所となるためには、その事業所の従業員の2分の1(半数)以上の同意を得なければなりませんが、2分の1(半数)以上の同意があれば加入を希望しない従業員も含めて適用することになります。
社会保険に加入する以上、事業所単位で加入することになります。
健康保険を扱っている医療機関に受診した場合、健康保険被保険者証を提出する
ことで、医療費の7割が給付され、残りの3割が自己負担となります。
≫≫詳細(全国健康保険協会)
療養の給付と同様に被保険者証を医療機関に提出することで医療費の7割が給付され、残りの3割が自己負担となりますが、3歳未満の家族については、医療費の8割が給付され残りの2割が自己負担となります。
≫≫詳細(全国健康保険協会)
やむをえない事情で健康保険を扱っていない医療機関に受診した場合や、健康保
険被保険者証を医療機関に提出することができない等の場合には、本人が医療費を全額立替払いし、あとで医療費の一部が払い戻されます。
≫≫詳細(全国健康保険協会)
1ヶ月に1つの医療機関に支払った医療費(自己負担額)がある一定額を超えた場合、超えた部分の医療費について払い戻されます。ただし、保険外(保険のきかない歯科材料、入院時の特別室料差額など)については、対象外となります。
≫≫詳細(全国健康保険協会)
病気や怪我で療養のため4日(うち始めの3日間は連続していること)以上仕事を休み、その間に給与の支払を受けていない場合、仕事を休んだ日1日につき標準報酬日額の3分の2相当額を受けることになります。
≫≫詳細(全国健康保険協会)
被保険者や被扶養者である家族が出産した場合、支給額は、1児につき42万円(産科補償医療制度加入の医療機関、それ以外は39万円)を原則、医療機関の窓口で、その額に足りない場合は差額を支払い、上記の金額の範囲内の場合は協会けんぽに請求します。
≫≫詳細(全国健康保険協会)
出産のために仕事を休み給与の支払を受けていない場合、仕事を休んだ日1日につき標準報酬日額の3分の2相当額が出産日(出産予定日)以前42日(多胎妊娠98日)から出産日後56日の範囲で受けることができます。
≫≫詳細(全国健康保険協会)
被保険者が亡くなったときは、埋葬料として一律5万円が支給され、家族以外の方が葬儀等を行った場合は、5万円の範囲内でその実費が埋葬費として支給されます。
≫≫詳細(全国健康保険協会)
新入社員は、入社の日など事実上の使用関係に入った日が、被保険者の資格取得の日となります。「事実上の使用関係に入った日」とは報酬が発生する日をさします。
たとえば、4月1日に採用され、4月10日に勤務を始めたという場合には、給料・賃金の支払関係により資格取得日が決められます。
①1ヶ月の給料が支払われる場合 ⇒ 資格取得日は4月1日
②日割計算で給料が支払われる場合 ⇒ 資格取得日は4月10日
パートタイマーの場合は、就労形態や内容を総合的に考えて、常用的使用関係にあると認められれば被保険者となります。
常用的使用関係にあるかどうかの目安としては、①1日又は1週間の勤務時間と②1ヶ月の勤務日数が、それぞれ同様の業務に従事する正社員のおおむね4分の3以上ある場合は、被保険者とするのが妥当とされています。
退職した場合には、退職した日の翌日に被保険者の資格を失います。
なお、被保険者資格は以下に該当する日の翌日に失うこととなります。
① 適用事業所に使用されなくなった日(退職日)
② 死亡した日
③ 雇用形態が変わり、適用除外になった日
④ 事業所が廃止になった日
また、上記①、③、④に該当した場合は、国民年金の第1号被保険者となりますので14日以内にお住まいの市区町村役場の国民年金窓口で手続をすることになります。
適用事業所に勤務していても、70歳になると厚生年金保険の被保険者資格を失うことになります。この場合の「資格喪失年月日」は、誕生日の前日となります。
尚、健康保険は年齢に関係なく在職中は加入することになります。
|

